なぜ日本の水族館から ラッコがいなくなる のか?
近い将来、日本の水族館でラッコがみられなくなってしまう日がくるのをご存じだろうか?
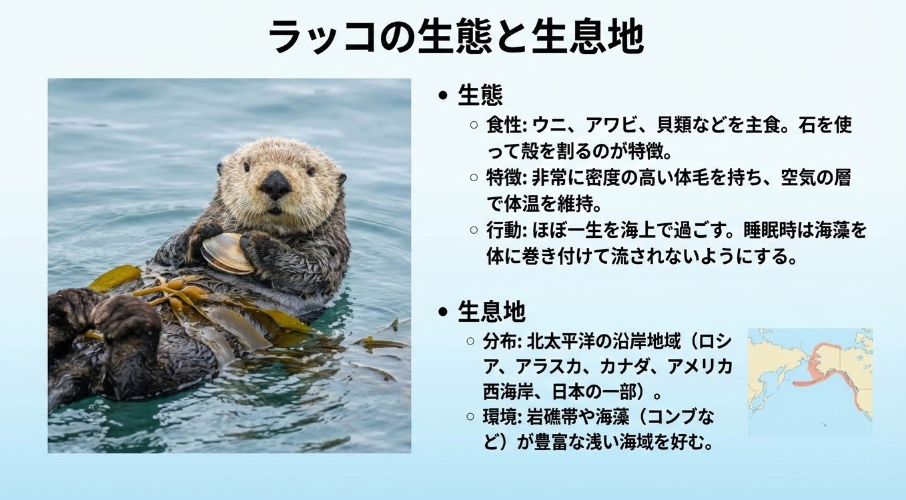
日本で飼育されているラッコは現在雌2頭のみとなっており、国内での繁殖は事実上不可能となっている。
1994年には122頭が飼育されていたが、現在は高齢のラッコ2頭のみだ。
この記事ではなぜ日本国内のラッコがここまで減ってしまったのか解説する。
Table of Contents
人工飼育下での繁殖が難しい
日本の水族館におけるラッコの人工飼育の歴史は、1982年に静岡県の伊豆・三津シーパラダイスで始まったとされる。
アメリカから輸入されたのが最初で、その後、鳥羽水族館などで繁殖に成功し、1980年代には日本でラッコブームが起こった。
しかし、ラッコは繁殖が難しく現状ここまで頭数が減った形だ。
ラッコは非常にデリケートな動物で、環境の変化や騒音、他の個体との相性など、様々な要因でストレスを感じやすい。
また、ラッコは通常、一度に1頭しか子供を産まないため繁殖が成功しても個体数の大幅な増加が見込めない。
ラッコの輸入制限

ワシントン条約や生息地の環境悪化により、海外からの新たなラッコの入手が非常に困難となっている。
ラッコは国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおいて、2000年に絶滅危惧種に指定された。
ラッコが絶滅の危惧にさらされている要因は下記だ。
①毛皮を目的とした乱獲
18世紀から19世紀にかけて、高価な毛皮のために多くのラッコが捕獲され、一時は絶滅寸前まで減少。
➁環境汚染
油田開発やタンカー事故による海洋汚染は、ラッコの体温維持に必要な被毛の機能を奪い、大きな被害をもたらしている。
➂生息地の破壊
沿岸開発や人間活動による生息地の減少が、ラッコの生存を脅かしている。
これにより、1998年以降、アメリカからの輸出は原則禁止となり、2003年のロシアからの輸入が最後となっている。
日本の法律によるラッコの保護
かつて日本列島ではラッコは絶滅したと考えられていたが、近年、北海道東部(主に道東)で野生のラッコの生息が確認されている。
特に根室市のモユルリ島や、浜中町の霧多布岬周辺で目撃情報が多く、霧多布岬では繁殖も確認されている。
これらの野生のラッコは、北方四島周辺から回遊してきた可能性が指摘されている。
このように、日本のラッコは飼育下では非常に数が減っているが、北海道の一部では野生の個体群がわずかに回復してきている。
しかし、野生のラッコの生息数も依然として少なく日本国内においても、「猟虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)」という法律で、ラッコの捕獲は原則として禁止されている。
国内でラッコの捕獲を禁止する法律があるため、基本的に野生のラッコを水族館に連れていくことはできないのだ。
まとめ
日本の水族館でラッコがみられなくなる理由についておわかりいただけただろうか?
現在は三重の鳥羽水族館で2体の個体が見れるので、ぜひ見に行ってほしい。

